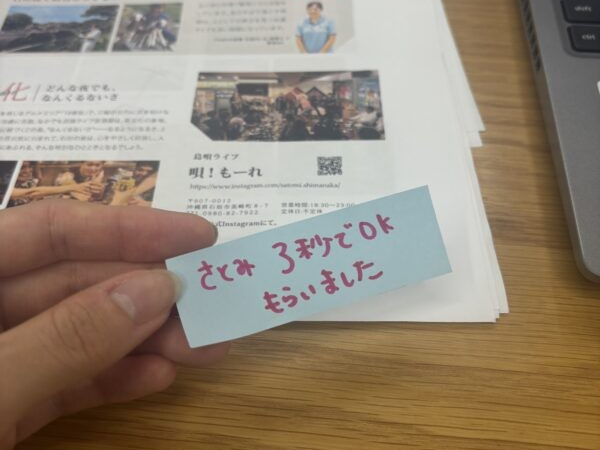なんとなく今こそ読むべき気がして本屋さんに寄ったらやっぱり特集されていた。
『アンネの日記』――ユダヤ人のアンネ・フランクがナチスの迫害に逃れながら屋根裏に隠れて暮らした2年間を綴った日記だ。
「よくわかる!歴史マンガシリーズ」みたいなのでキュリー夫人やマリーアントワネットに並んで彼女の名はあった。
その時わたしはマンガの読みたさに手を取り学童のカーペットに寝っころがって読んだけど、いつかは活字で読もうと思っていた。
気づけばこんな世の中になっている。
アンネ・フランクは1929年6月12日生まれ。
日本でいうと昭和2年生まれだ。
私の勤める施設は平均年齢が90歳前半、つまり昭和2年〜6年生まれの方が多い。
普段接するご入居者はアンネとほぼ同い年なのだ。
よく考えれば、疎開の話は普段からよく聞かせてもらっているし
「あなたはいつもパンの焼きが甘い」と怒らせてしまうおじいさんは満州に行って弾丸で腕をなくしかけている。
同じ戦時下を生き抜いてきた方々なので同い年でも当然あり得ることだが、私の認識ではアンネはすでに歴史上の人物だったので、今手を引いて隣を歩くおばあさんがアンネの同級生だと気づいた時は妙な気持ちになった。
当時14歳のアンネは日記にこう書いている。
とにかく、ママたちとはどうにも気が合いません。うちの家族のベタベタした関係には、もううんざり。(中略) なのにママたちは、こうして4人一緒に暮らせて、しかもこんなに仲良くやっていけるのは、どんなに幸せか、そんなことばかり言って、ひょっとしたらこのわたしなんか、ぜんぜんそんなふうに感じていないかもしれない、などとはこれっぽっちも考えたことがないみたい。
もう学校では新学期が始まっているところです。こちらも一所けんめいフランス語を勉強し、毎日5つずつ不規則動詞を暗記するようにしています。それにしても、学校で習ったことを早くもごっそり忘れちゃってるので、これには我ながら呆れてしまいます。
なぜか人差し指がひどく傷んで、今のところアイロンかけは全然できません。ラッキー!
彼があの笑みを含んだ目でわたしを見、ウインクすると、わたしの中で、小さな光がぽっとともるみたいに感じます。どうかいつまでもこれが持続しますように。
―アンネ・フランク(2003) 増補新訂版 アンネの日記 文春文庫
アンネが日記に向かっていた75年前と、今日の世界とでは、どれほどの違いがあるというのでしょう。
さっき廊下を一緒に歩いたおばあさんも、生まれた国や環境が違うとはいえ、戦時下での思春期が確実にあった。大人は誰でも子どもだったなんて、そんなことは分かっちゃいたけれど、異国の少女の日記を読んで初めて、それがリアルに思えてくる。
私は今、生き抜いた日本のアンネと同じ歴史を重ねて生きているんだ。
そう思うと背筋が伸びた。

施設に勤めるようになってもうすぐ2年、昔の流行歌をたくさん教わったし、唱歌も大抵歌えるようになった。
音楽の力はやはりすごくて、私の拙いピアノ伴奏でも涙を流して喜んでくださる方もいる。
今、ここのカラオケ定番曲といえば坂本九の「上を向いて歩こう」だが、
昭和1ケタ生まれの方が天寿を全うしご入居者の平均が昭和10年代、20年代と入れ替わっていくに連れて坂本九が都はるみに、テレサテンに、フィンガー5に、カラオケの履歴もゆっくりと流行の跡を辿っていくのだろう。
当時の日本の音楽シーンの流れが、60年後の老人ホームで再現されていく。
もちろん私も同じだけ年を取っていくので、私や、私の友人らが施設に入居した20XX年台の暁には、嵐やあいみょんで涙を流しテイラースウィフトで健康体操している老人が続出するのかもしれない。

今年も、アンネと1日違いで生まれたご入居者の車椅子を押して近くの郵便局まで桜を見に行くことができた。
綺麗ですねー!と笑って話せたこと、空の青さに映える桜がなんとも美しかったこと
この仕事をしていると、たまに映画のワンシーンかと錯覚するような光景に出会って泣きそうになる。それは別れの近さがそうさせているのかもしれないし、御神木みたいになった皺くちゃの体にしか宿らない古いやさしさみたいなものがあるのかもしれない。